ある日、店に迷子のコインがやってきた。情報ゼロ──でも手に取るとただ事じゃない“気配”。両面に放射する三叉矛(トリシューラ)。徹底調査の結果、古代インドでは“中央銀行の前に中央寺院があった”という、信仰と経済が一体化した仕組みが浮かび上がった。寺院トークンが証明する「行動と関係性が通貨になる社会」を、現代の通貨システムと重ねて解剖する。
🔍プロローグ:迷子のコインが語るもの
「これ調べてみてよ」と店主から手渡された1枚。文字なし・国名なし。でもずっしり重くて分厚い。両面には三叉矛(トリシューラ)が5方向に放射。…これはただの装飾じゃない。触れていると、千年の祈りの残響が指先に乗る。

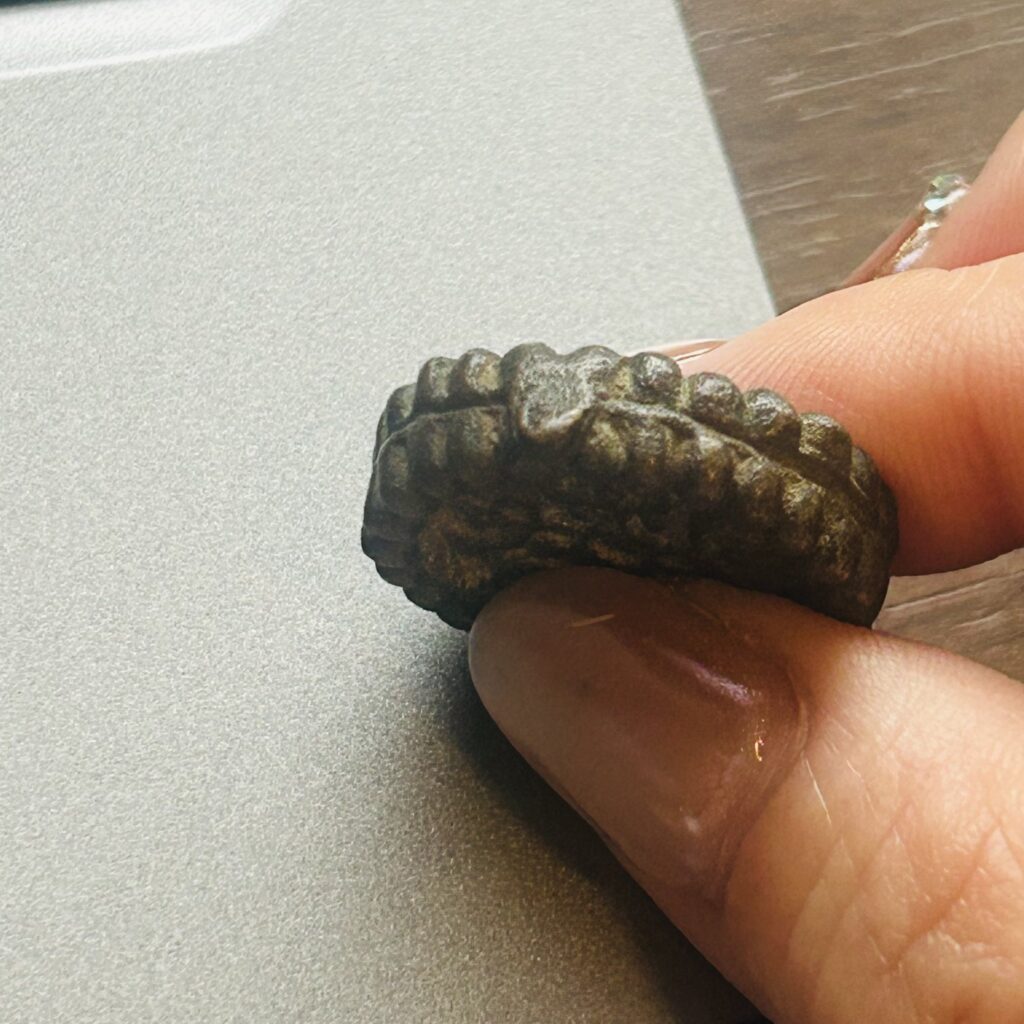

🪙コインスペック(仮説)
- 地域:北〜中央インド(マールワ〜カーリンガ地方?)
- 時代:11〜13世紀
- 素材:銅合金(ビロン系?)
- サイズ:約25mm/約13g(通常銅貨より重厚)
- 特徴:三叉矛=シヴァ信仰の象徴/5方向放射モチーフ
- 製造:打刻でなく上下鋳型の立体鋳造(精度高く私鋳の可能性は低い)
👉総合すると【寺院内鋳造のトークン】とみるのが濃厚。
🛕なぜ寺院が“通貨”を作ったのか
当時のインドは小王国が乱立し、統一通貨は希薄。地域の信用ハブは寺院だった。奉納を受け、労働を配分し、信頼を可視化する印としてトークンを発行──いわば**「中央寺院=地方の中央銀行」**である。
🕉寺院トークンのリアル運用
- 奉納・神事奉仕の対価として付与(=信仰と労働の証)
- 寺院や市場で日用品購入・賽銭として流通
- 村の職能(ジャーティ)層の報酬にも使用
🪙=「奉仕と関係性の可視化」。
“誰がコミュニティを支えたか”を記録する信用メディアだった。
🔮ヒンドゥー教が根づいた“構造的な理由”
ヒンドゥーは単なる思想ではなく社会運営のOS。
- 経済=寺院トークン
- 職能=カースト分業
- 規範=信仰と祭祀
対して、仏教は出家理想に重心が寄り地域経済へ浸透しづらく、イスラムは王朝文化として華やかでも民衆の言語・職能構造を置換しきれなかった。社会実装の深さでヒンドゥーに軍配。
✴️まとめ:行動が通貨になる社会
中央銀行より“中央寺院”が先にあった国・インド。
🛕奉納する人/🛠祭りを支える人/🫱誰かのために動く人──その行動の積み重ねが信用となり、通貨として巡った。
⚡現代への問い
今の通貨は発行主体が遠く、利用は追跡され、数字の履歴で信用が決まる。CBDCの到来は“中央寺院”の再演でもあり、真逆でもある。だからこそ問い直したい──私たちはどんな経済を望む?
アンティークコインは、ただの金属ではなく人類の思想そのものだ。
こちらのコインは、週末店頭に並ぶ予定です。ぜひ手に取って、1000年前の“信頼経済”を感じてください🧸
3ポイントまとめ
- 寺院が地域の信用ハブ=トークン発行で“中央寺院”が機能
- トークンは奉仕・祭祀・関係性を可視化する信用メディア
- 古代の「関係性経済」を手がかりに、CBDC時代の通貨観を問い直す
引用元




コメント